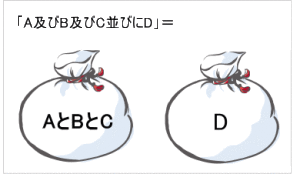及び
「A及びB」
「A、B及びC」
「A、B、C及びD」
並びに
「A並びにB」 ※「A及びB」との厳密な使い分けは不明
及びと並びとの関係
「(A及びB)並びにC」
「(A、B及びC)並びにD」
「(A及びB)並びに(C及びD)」
「(A及びB)、(C及びD)並びにE」
又は、若しくは
又は
「A又はB」
「A、B又はC」
「A、B、C又はD」
若しくは
「A若しくはB」 ※「A又はB」との厳密な使い分けは不明
又はと若しくはとの関係
「(A若しくはB)又はC」
「(A、B若しくはC)又はD」
「(A若しくはB)又は(C若しくはD)」
「(A若しくはB)、(C若しくはD)又はE」
<補足>
・「A、B、C、及びD」や「A、B、C、又はD」のように句読点(下線部)を打つこともあるようですが、厳密なルールはないようです。
・「又は」「若しくは」と同じ意味で「或いは(あるいは)」もありますが、使うことはほとんどありません。
・「乃至(ないし)」は、一般的に「又は」と同じ意味で使われていますが、法律用語的には「●●から△△に至るまで」の意味で使われています。例:請求項1乃至3のいずれか一つに記載の・・・
「若しくは」「又は」、「及び」「並びに」の使い分け
憲法の条文から具体例をあげる。
●単純に2つを並べる時は「又は」「及び」を用いる。
(例)国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。(第17条)
(例)思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。(第19条)
●3つ以上並べる場合
○並列の場合は最後のつなぎにのみ「又は」「及び」を用い、あとは読点「、」を打つ。
(例)生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利(第13条)
○大小がある場合は「若しくは」<「又は」、「及び」<「並びに」
(例)配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては(第24条)
(解説)「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚(以上5件が並列扱い)」と「婚姻及び家族(以上2件が並列扱い)に関するその他の事項」が同格で並列。
(これを大小関係を逆に読むと,「配偶者の選択~婚姻」がひとまとまりで6つ並列になりますが,そうすると財産権と婚姻が並列になっておかしいですね。)
(「、離婚」を「及び離婚」としても同じ。)
(例)強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。(第38条)
(解説)「強制、拷問若しくは脅迫(以上3件が並列扱い)による自白」と「不当に長く『抑留若しくは拘禁』(以上2件が並列扱い)された後の自白」が同格で並列。
- 「かつ」は条件が常に両方成立することを示す。
(例)何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。(第34条)
(例)最後に少し長いですがよく出てくる例として地方自治法第152条から。
1 普通地方公共団体の長に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は助役がその職務を代理する。(以下略)
2 副知事若しくは助役にも事故があるとき若しくは副知事若しくは助役も欠けたとき又は副知事若しくは助役を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公 共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、当該普通地方公共団体の長の指定する吏員がその職務を代理する。(以下略)
(解説)第1項は普通の「又は」が使われている。複雑な第2項は次のように理解する。
「(副知事若しくは助役)にも事故があるとき
若しくは
(副知事若しくは助役)も欠けたとき」
又は
「副知事若しくは助役を置かない普通地方公共団体において
(当該普通地方公共団体の長に事故があるとき
若しくは
当該普通地方公共団体の長が欠けたとき)」
は、…
以上、大小3段階の構造の場合は
「若しくは(小)」<「若しくは(大)」<「又は」
「及び」<「並びに(小)」<「並びに(大)」
となっていることがわかる。
2つの「若しくは」を区別する時は、「大若し(おおもし)」「小若し(こもし)」、「小並び」「大並び」と通称している。